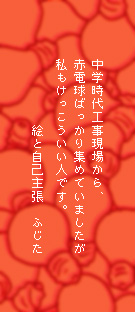 酒乱というのは、やはりふだんおとなしいひとが多いようである。
酒乱というのは、やはりふだんおとなしいひとが多いようである。
むかし勤めてた会社の後輩がそうだった。
僕がいっしょのときは、たまたま荒れたところを見せたことはなかったが、「あいつにはあまり飲ませないほうがいいですよ」と、よく耳にした。
あるとき、彼とふたりで飲んで、店を出た。だいぶ飲んで、彼は口数がすくなくなっていた。
ひと気のない暗い道を渋谷駅に向かって歩きながら、ふと横顔を見ると、彼の眼がすわっていた。
あぶないな、と思い、かまわないようにしながら黙って歩きつづけた。
すると、隣を黙々と歩く彼は、工事現場につらなる赤い三角帽子のようなパイロンを、下げていた鞄で、ぽーん、ぽーん、とひとつずつ倒していく。
僕は、そのようすを眼のはしにとらえつつ、駅へと向かう足どりをじょじょに早めたのであった。
まったく、飲んでも飲まなくてもいいヤツといったら僕くらいなものである。
